てんかんの診断方法
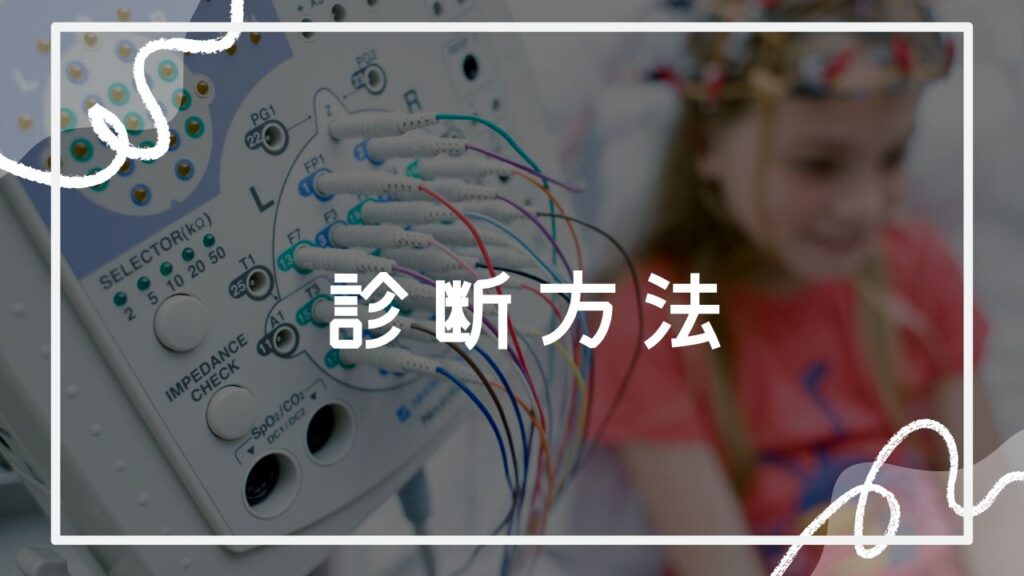
てんかんの診断方法は、主に 問診 と 検査 によって行われます。
1. 問診による診断
問診は、てんかんの診断で最も重要なステップです。発作の様子や背景情報を詳しく聞き取ることで、発作の種類や原因を特定し、適切な治療方針を決定します。
- 発作時の詳細な様子(意識の有無、けいれんの部位や時間、前兆の有無など)
- 発達面の問題(知能や行動の遅れなど)
- 家族歴(てんかんの家族歴があるか)
- 既往歴(頭部外傷、熱性けいれん、脳疾患の有無など)
発作時の動画を撮影することも、診断の参考になることがあります。
2. 検査
問診に加えて、以下の検査を行い、診断を確定させます。
(1) 脳波検査
- 通常の脳波検査:脳の電気活動を記録し、てんかん特有の波形(棘波や尖波など)を確認します。
- 長時間ビデオ脳波モニタリング:数日間にわたり脳波を連続測定し、同時に映像を記録して発作時の様子を解析します。
(2) 脳画像検査
- MRI(磁気共鳴画像法):脳の構造を詳細に観察し、てんかんの原因となる病変(脳腫瘍、海馬硬化など)を確認します。
- CT(コンピュータ断層撮影):主に緊急時に、脳内出血や脳の異常構造を確認するために用います。
3. 診断の流れ
- 問診 で発作の様子や背景を詳しく聞き取る。
- 脳波検査 でてんかん特有の波形を確認する。
- 脳画像検査 で脳の構造に異常がないかを確認する。
- 必要に応じて、血液検査 や 遺伝子検査 を追加し、他の疾患を除外する。
4. 診断後の対応
- 小児の場合:小児科を受診。
- 成人の場合:神経内科、脳神経外科、または精神科を受診。
- 専門的な診断・治療を受ける場合は、てんかんセンター の受診を検討します。
5. 注意点
てんかんと似た症状を示す他の疾患(例:熱性けいれん、急性脳症、髄膜炎など)との区別が必要です。そのため、詳しい問診と適切な検査を組み合わせて診断します。
参考情報
てんかんの診断は複雑であり、専門医による総合的な評価が必要です。もし心配な症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。


