ダウン症のある子どもの生活での困りごと
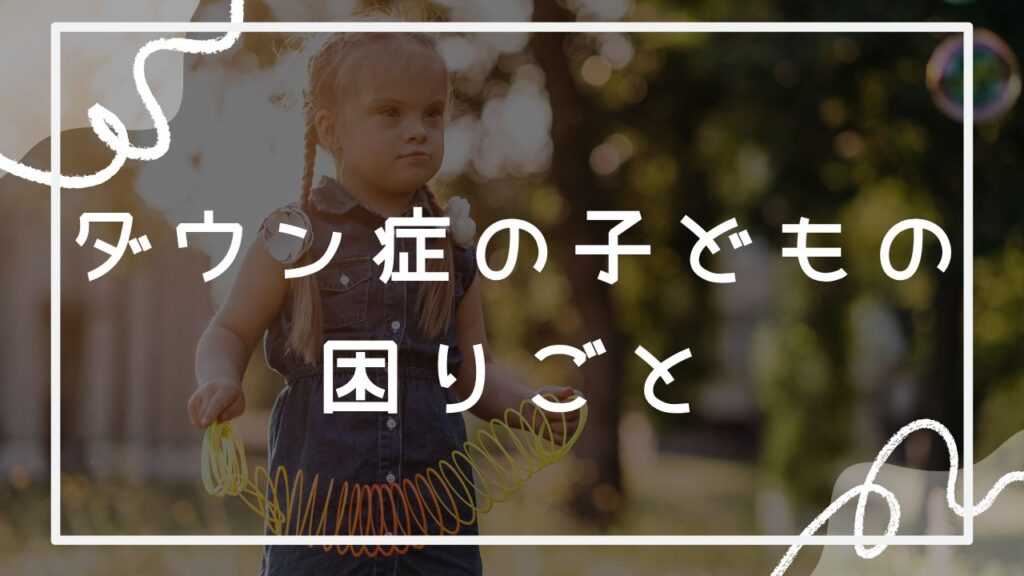
ダウン症のある子どもの生活での困りごとは、成長段階ごとに異なります。以下のように「乳児期」「幼児期」「児童期以降」に分けて詳しく見ていきましょう。
乳児期の困りごと
- 合併症のリスク:心臓疾患、消化器系の異常、免疫力の低さなどがあるため、体調管理に細心の注意が必要です。
- 筋緊張低下:筋肉の緊張が低く、母乳やミルクをうまく吸えないことがあります。また、泣く力が弱く、空腹や体調不良に気づきにくいことがあります。
- 対応策:
- 哺乳瓶を使った授乳や、穴の大きい乳首を選ぶなどの工夫をする。
- 体調のチェックをこまめに行い、ゆっくり時間をかけて授乳する。
幼児期の困りごと
- 自我の芽生えとこだわりの強さ:決まった服しか着たがらない、同じ道を歩きたがるなどの行動が見られることがあります。
- 知的発達の遅れ:言葉の発達が遅かったり、理解や行動がのんびりしていることがあります。個人差はあるものの、数ヶ月~半年程度の遅れが見られ、成長に伴い差が大きくなることがあります。
- 肥満のリスク:代謝が低く、肥満になりやすい傾向があります。
- 対応策:
- 気持ちを尊重し、こだわりに付き合うことで安心感を与える。
- 食生活の管理や、適度な運動を習慣化して肥満を予防する。
児童期以降の困りごと
- 学習面での困難:
- 通常学級では授業についていくことが難しくなる場合があります。特に、耳からの情報理解が苦手で、一斉指示を理解しにくいことがあります。
- 中学・高校に進学するにつれて、特別支援学級や特別支援学校を選択するケースが多くなります。
- 二次障害のリスク:
- 不安障害、うつ病、不登校、依存症などの二次障害が思春期以降に現れることがあります。
- 対応策:
- 本人が生きづらさを感じない環境づくりが重要です。
- 医療機関の受診や相談機関の利用を積極的に行う。
子育てのコツと工夫
- わかりやすい言葉でじっくり説明する:発達に応じた言葉を使い、理解を促す。
- こだわりを否定しない:ルーティン行動は本人の安心感につながるため、温かく見守る。
- 個性を伸ばす:本人の好きなことや得意なことを見つけて、ポジティブに伸ばす。
- 日常生活に結びつけて学ぶ:実生活での体験を伴う具体的な学習を通じて、知識の定着を図る。
- 姿勢を保てる工夫をする:筋緊張低下に対応して、座りやすい椅子や机を選ぶ。
- 理解してくれる友達をつくる:本人を理解してくれる仲間づくりを支援する。
- 療育に通う:療育を通じて、環境設定や学習の支援を受ける。
- 親自身のストレス管理:保護者がリラックスして過ごすことで、子どもも安心して過ごせる。
まとめ
ダウン症のある子どもは、一人ひとり個性や性格が異なります。特性を理解し、得意なことを伸ばしながら、適切なサポートを行うことが大切です。困りごとがあった場合は、医療機関や相談機関を利用して、周囲のサポートを得ながら進めていきましょう。


